


時代を超えて愛され続けるZARDを支えたスタッフが語る、音楽の届け方
株式会社ギザ チーフディレクター 寺尾 広
株式会社BIRDMAN MASTERING マスタリングエンジニア 島田 勝弘

音楽業界で輝く方にスポットライトを当て、彼らの仕事や想いを通して音楽業界の今と未来を伝える新企画、3rd Lounge。
第4回は時代を超えて愛され続けるZARDを長年支え、多くの人に届けてきたビーイングの音楽ディレクター・寺尾 広氏とレコーディング・マスタリングエンジニア・島田 勝弘氏が登場。
ZARDは今年で30周年を迎え、オリジナルアルバムのリマスター盤発売やサブスク解禁も発表され、今なお注目を集めている。
今回も音楽ルーツやターニングポイント、仕事をする上で大事にしていること、これからの音楽の届け方などについて話を聞いた。
今回のインタビュアーはモデル業を中心に、音楽系のラジオパーソナリティなども務め、多彩な活動で注目を集め続けている菅野結以が務める。
Chapter.1
二人の音楽ルーツとターニングポイント

菅野:まずはお二人の音楽との出会いを教えてください。
寺尾:僕は母親が家でピアノの教師をやっていて、ピアノの発表会に無理矢理出させられたんですよ。それがすごく嫌で、小学生になったら絶対にやめようと思っていて(笑)、「やめたい」って言ったら、あっさり「いいよ」って言われたんですね。それで、一旦ピアノはやめたんです。
その後、高校に入って学校が嫌になった時「よし、音楽をやろう」と思って、初めてちゃんと音楽に向き合おうとしたんです。それでピアノを弾こうと思ったら、やっぱりあんまり弾けなくて(笑)。それからビートルズの耳コピから始めて、世の中を変えるような曲を作ろうと思って曲作りを始めました。その頃、たくさんの音楽に出会いました。ビートルズ、ザ・ローリングストーンズ。60年代のイギリスのロックや、ラテン、ジャズ、ブルース。邦楽ではキャロル、山下達郎さんが好きでした。

菅野:ご自身が表に出るのではなく、支える側になろうと思われたのは、何かきっかけがあったんでしょうか?
寺尾:大学に入ってバンドをやったんですけど、自分には無理だなと思ったので諦めたんですよ。その後普通の会社に就職したけどすぐに辞めて、ミュージカルをやっている小さい劇団の劇団員もやったりしていたんですけど、裏方として音楽を届けるという仕事があるはずだと思って探した中にビーイングがあって、そこで採用していただいたという感じです。
菅野:島田さんの音楽ルーツを教えてください。
島田:僕が音楽を聴き始めたのは中学生ぐらいですかね。当時、土曜日に『ビートポップス』という、洋楽のベストテンみたいなテレビ番組があったんですよ。それと、同じ土曜日にFMラジオで日本の音楽のベストテンみたいな番組があって、その2つでよく音楽を聴いてました。ビートルズやサイモン&ガーファンクル、70年代初めは「なごり雪」のイルカやかぐや姫、70年代中期辺りはイーグルスやクイーンをよく聴いていましたね。
70年代の後半に大学に入って、それまでは聴く側だったのが、軽音楽部でドラムをやり始めて演奏する側になったんですが、全然上手くなくて(笑)。ミュージシャンにはたぶんなれないだろうなと思うようになって、そこからミキサーの専門学校に行って。その頃、ビーイングがスタジオを作るということで募集を出していたので応募しました。でもスタジオじゃなくて別の部署で採用されて、マネージャーをやったりしていました。
菅野:マネージャーさんをされていた時期もあったんですね。
島田:THE 虎舞竜の前身バンドがビーイングにいて、担当していたんです。そこでいろいろな職種を体験した後、アシスタントエンジニアを経てエンジニアになりました。

菅野:お二人ともビーイングに入って音楽のお仕事を始められましたが、ご自身にとってターニングポイントになった出来事がありましたら教えてください。
島田:僕がアシスタントエンジニアになった時に、佐藤博さんというミュージシャンの方がいて、DREAMS COME TRUEのライブの音楽監督とか、山下達郎さんのピアノレコーディングなど、いろいろとされていた、マルチプレーヤーだったんですよ。その佐藤さんが、ビーイングのスタジオでご自身のソロアルバム「SAILING BLASTER」を作った時に、僕がアシスタントについたんですが、佐藤さんの音楽的アプローチに影響を受けました。音楽に携わるにあたっての、マルチプレーヤーとしてのアプローチですよね。現在こそ主流になっていますが、佐藤さんは当時からコンピューターで打ち込んで、一人多重録音されていたんですよ。
寺尾:今、自分の家で打ち込みをしてレコーディングしている人が多いですけど、その走りみたいな方ですよね。
島田:そう。40年ぐらい前からやってたから。
菅野:先駆けのような方との出会いが大きなターニングポイントだったんですね。寺尾さんはいかがですか?

寺尾:ターニングポイントはビーイングに入ってから何回かあるんですけど、最初に感じたのは、とあるバンドのアシスタントディレクターをやっていた時に、今回のアルバムのイニシャル(初回注文)があんまり取れてないから、次の作品で何か画期的なことをやってイニシャルを稼ぐ方法を考えろ、とレコード会社のディレクターに言われたことがあって。その時にバンドメンバーと「売れている音楽をもっとちゃんと研究するべきだ」という話になって、売れているいろいろな洋楽ミュージシャンの話が出たんです。その時に僕は「しまった」と思ったんですよ。バンドのメンバーに比べて、僕はあまりにも知らなすぎだなと。世の中のたくさんの人に音楽を届けたいのに、みんながいいなと思っているものを知らずに作る、というのは間違っているなと、すごく反省しました。それで慌てて、その時に流行っている音楽や、過去に遡って流行っていたものを研究していきました。みんながいいなと思っている音楽のどこがいいのかということを、もう一回再確認するために聴いたりしましたね。
若い時はどうしても自分がカッコいいと思う音楽に傾倒しがちです。その後、ビーイングの創業者である長戸大幸プロデューサーから直接、多くの人に支持される音楽の秘訣をたくさん教われたことが、僕の音楽人生を変えてくれました。
他にもいろいろあります。例えば音楽のミックス確認をする時に長戸さんはラジカセで聴くんですよ。今で言うとiPhoneやパソコンで聴くようなものですよね。要するに、リスナーが聴いている環境と同じ環境で聴くべきだ、ということなんです。ユーザーに届ける時にはそういう配慮でやるべきだなと。それも今の僕の原点の一つになっています。
Chapter.2
ZARDを現代に届ける上で大事にしていること
菅野:続いて、ZARDについてお聞きしたいと思います。ZARDは現在に至るまで、多くのリスナーの方に届くような様々な施策をされていて、そういった施策がある度に話題化され、レコチョクランキングをはじめ、チャート上位にも入ってくるイメージがあります。企画をされる際に、工夫されていることはありますか?


寺尾:施策に関しては、企画をしているというよりも、いろいろとお声掛けをいただくので、その都度やっているという感じに近いかもしれないですが、ZARDが受け入れられているのは、コンセプトを明確にもったこと、そしてそれが現代にも受け入れられやすかったこと、というのが要因だと思っています。
ZARDの坂井泉水さんは元々、B.B.クイーンズのコーラスを決めるオーディションに来た一人だったんです。その後、坂井泉水さんをボーカルに、アン・ルイスさんとテレサ・テンさんの間くらいの感じのロックバンドを作ろうということになったんです。
まず、長戸さんはZARDの描く世界観について、どちらかというとインドアで、積極的に外に遊びに行くのではなく部屋にいて、ちょっとスーパーやコンビニに行く程度の人で、だからそんなにメイクをする必要がないし、髪も簡単に結んであるだけ。まず、そういうコンセプトを最初に決めたんです。
歌詞は彼女が書き続けていたんですけど、それも昭和の女性、古風な女性を描いていて。たとえば恋愛について、自分から別れていくのが阿久悠さんだとしたら、「私を捨てないで」とすがるのがなかにし礼さん。ZARDはそのどちらでもなくて、「ごめん、自分の夢があるからアメリカに行って修行するわ」って言われたら「わかりました」って言って、そこにとどまってその夢を応援する、とういうスタンスの女性を描き続けたんです。
90年代でいうと服に肩パットが入っていたり、眉毛を剃っていたりといったブームがありましたが、彼女はずっとナチュラルな感じのままだったので、今見ても時代を感じないんですよ。古くもなく違和感もないというか。そういう工夫をずっとしていたことが、結果として今でも受け入れられているのかなと思いますね。
寺尾:施策に関しては、企画をしているというよりも、いろいろとお声掛けをいただくので、その都度やっているという感じに近いかもしれないですが、ZARDが受け入れられているのは、コンセプトを明確にもったこと、そしてそれが現代にも受け入れられやすかったこと、というのが要因だと思っています。
ZARDの坂井泉水さんは元々、B.B.クイーンズのコーラスを決めるオーディションに来た一人だったんです。その後、坂井泉水さんをボーカルに、アン・ルイスさんとテレサ・テンさんの間くらいの感じのロックバンドを作ろうということになったんです。まず、長戸さんはZARDの描く世界観について、どちらかというとインドアで、積極的に外に遊びに行くのではなく部屋にいて、ちょっとスーパーやコンビニに行く程度の人で、だからそんなにメイクをする必要がないし、髪も簡単に結んであるだけ。まず、そういうコンセプトを最初に決めたんです。
歌詞は彼女が書き続けていたんですけど、それも昭和の女性、古風な女性を描いていて。たとえば恋愛について、自分から別れていくのが阿久悠さんだとしたら、「私を捨てないで」とすがるのがなかにし礼さん。ZARDはそのどちらでもなくて、「ごめん、自分の夢があるからアメリカに行って修行するわ」って言われたら「わかりました」って言って、そこにとどまってその夢を応援する、とういうスタンスの女性を描き続けたんです。
90年代でいうと服に肩パットが入っていたり、眉毛を剃っていたりといったブームがありましたが、彼女はずっとナチュラルな感じのままだったので、今見ても時代を感じないんですよ。古くもなく違和感もないというか。そういう工夫をずっとしていたことが、結果として今でも受け入れられているのかなと思いますね。
菅野:なるほど。そういうコンセプトがあったことにより、結果、揺るぎない存在になっていったんですね。島田さんはこれまでの企画の中で、印象に残っていることはありますか?
島田:やっぱり、寺尾さんが言う通り、企画というよりも、その時々で最高のものを作ってきたから、という印象があります。歌い直すこともそうですが、アレンジ、ミックスをし直すときに、その時代時代で自分たちが納得のいくものを、時間をかけて作っていったことが、後々どんなものにでも対応できるものになっているんじゃないかなと思います。
菅野:1曲完成するのに8カ月もかかった曲もあったそうですね。
寺尾:「運命のルーレット廻して」がそうですね。島田さんと坂井さんとで歌入れをして、それを僕が選ぶ。坂井さんが「歌は3トラックあるんですけど、2個目がいいと思うので、それを中心に選んでください」って帰られるわけですよ。で、聴いてみて「これはちょっと違うな」なんて思いながら選ぶと、また坂井さんが歌うんですよ(笑)。そのうちにアレンジが変わったりしながら、結局8カ月ぐらいやってましたね。最初は“え?また?”って思ってましたけど、だんだんと楽しくなっていきました(笑)。
島田:今思うと、そこまでやらせてくれるところって他にないですよ。予算の関係だとか日程の関係だとか、いろいろと問題が出てきますから。
菅野:9月15日(水)に30周年を記念したオリジナルアルバムのリマスター盤が発売になるのと同時に、400曲弱の全曲がサブスク解禁されました。サブスク解禁に踏み切った理由を教えてください。
寺尾:確かに踏み切りましたね。30周年というタイミングもあり、やっぱり、今の時代で多くの人に聴いていただくにはサブスクがいいかなと。あと、今、CDはコレクターアイテムだと思っているので、それも大事にしながら、より多くの方へ届けるには、を考えた結果、サブスク解禁をすることになりました。
菅野:島田さんはサブスクに向けて、何かされたことはありますか?
島田:サブスクのためにこうした、というのは基本的にはないんですけど、一曲の中で一瞬だけ急に音が大きく(True Peak)なったりすることがあったりするんですが、そういうところを抑えたりはしました。アルバムの曲に関しては、今回リマスターしたものからサブスク用に起こしています。なので、配信では、基本的にサブスクでしか聴けない最新音源が聴けるんですよ。今回のリマスターに関しては、歌が一番活きることを優先しました。やっぱり最終的にみなさんが聴くのは歌ですから。歌がメインで、それが一番よく聴こえるようになっています。

菅野:また、SARD UNDERGROUNDというトリビュートバンドを通してのアプローチも斬新だと思いました。
寺尾:長戸プロデューサーと出会った若いミュージシャンたちが、ZARDを練習したりしていたんですけど、その中で長戸さんが「トリビュートバンドをやってみないか」と持ちかけて始まりました。メンバーも最初はただただ嬉しかったみたいなんですけど、実際にやってみたらこれは大変だ、と緊張してしまったようでしたが、今は落ち着いて真摯に伝えてくれています。僕は、彼女たちを通して広くZARDを知ってもらうきっかけになっていると思います。もしもSARD UNDERGROUNDをオフィシャルとしてやっていなかったら、ZARDがアーカイブ化してしまったり、過去の音楽になる可能性が十分ありましたから。だけど、彼女たちが出てきたことで改めて聴いてもらえますし、中には小さなお子さんがご両親と一緒に聴いてくださっているという話も聞きますから、彼女たちには本当に感謝しています。
菅野:改めて、ZARDが長く愛されている理由はどんなところにあると思いますか?
島田:やはり曲ありきだと思います。そして坂井さんの歌とアレンジ。企画だとか営業だとか、売れる要素というのはいろいろとありますけど、やっぱり音楽、楽曲自体の力もすごく大事だと思います。
寺尾:僕もそう思いますね。制作過程の中で誰も手を抜かず、きちんと作ってきたものなので、時代を超えても古さを感じさせない。今後も、その時代にあったところで音質についていろいろと考えたりしますけど、基本的にはあまり変えないでZARDらしさをずっと提供し続けたいなと思っています。
Chapter.3
仕事をする上で大事にしているポイント、これからの音楽の届け方
菅野:お二人がお仕事をされるうえで大事にされていることはありますか?

島田:僕は音楽エンジニアって、基本は旅館の女将だと思っているんですよ。スタジオが良いに越したことはありませんが、旅館と同じく、スタッフのさりげない気配りやおもてなしが、来た人(歌う人)の心に一番残ると思うし、それが歌い方やパフォーマンスにも影響する部分だと思うので、エンジニアとしての技術云々の前に、気配りを大事にしています。スタジオに入ったら、まずはトイレ掃除から始めますから(笑)。
菅野:まさに女将の心!素晴らしいです。寺尾さんはいかがですか?
寺尾:僕は最終的には“気”だと思っているんですよ。今はデジタル化されてちょっと伝わりにくいかもしれませんが、やっぱり音楽というのはその時の気持ち次第で違う音になるんです。だから、島田さんがおっしゃっていたことにも通じると思うんですけど、スタッフみんなが円滑にいけるように気を配ったり、気持ちの入った録音、ミックスや、歌ったり演奏をすることも大切だと思っています。
菅野:コロナ以降、音楽業界は音楽の届け方をはじめ、様々な環境変化の渦中にあると思いますが、今後の音楽業界についてどんなことを思われますか?
寺尾:音楽の届け方は変わってきたと思いますが、やはり同じ話になりますけど、いいものを作り続けることが大事だと思います。昔はライブで、みんなで一緒に共感できていたけど、今はそれぞれが共感し合ってネットで「いいね」っていう時代だと思うので、いいものを作って、いいタイミングでSNSなどを活用しつつ拡散していけば、必ずや人に届いていくんじゃないかと思います。
島田:これまでアナログレコード、CDと、伝える媒体は変わってきてますけど、やっぱり音楽自体はずっと残っているので、いい楽曲、いい音楽を作っていければ、伝え方や伝える場所が変わっても残っていくと思います。なので、「良いものを作る」という姿勢があればいいかなと思っています。
菅野:最後にお二人にとって、音楽とは何かを教えてください。
寺尾:自分にとって、音楽はなくてはならないものですね。本当に音楽がなければ、僕には人として何もないかもしれないと思うくらいのものですね。
島田:音楽は、たとえば震災などがあった時に、リアルタイムでは命などが第一になると思いますが、音楽はその後で寄り添ってくれるもので、音楽で励まされたりだとか、心の拠り所になったりするところがあると思うんですね。そういう感じで、なくてはならないものというよりも、僕自身も、音楽があったから助けられたと思っています。

-

寺尾 広
(株)ギザ 制作部長兼チーフディレクター
(株)ビーイングに入社、ZARD、T-BOLAN、WANDSなど様々なアーティストのディレクター、また並行して作曲・編曲・キーボード・コーラス、なども行う。
またSoul Crusadersのメンバーとしてシングル3枚、アルバム1枚をリリース。
大阪に拠点を移し、」引き続き多岐に渡って活動中。 -
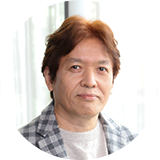
島田 勝弘
(株)BIRDMAN MASTERING代表 マスタリング エンジニア
(株)ビーイングでのレコーディング&マスタリング エンジニアを経て2013年に独立。現在はLIVE収録やMix及びマスタリング業務など幅広い活動を行う。
代表作はRec&Mix:B.B.クィーンズ「踊るポンポコリン」、ZARD「Good-bye My Loneliness」、WANDS「世界が終るまでは…」、Mastering:B’z「ultra soul」 -

菅野 結以
雑誌『LARME』『PECHE』などで活躍するモデル。10代の頃から『Popteen』専属モデルを務め、「白ギャル」の文化を生み出しカリスマモデルと称される。
スタイルブック、フォトエッセイ、写真集などこれまで7冊の著書を発売。
アパレルブランド「Crayme,」のディレクター及びデザイナーを務めている他、各企業とのコラボやプロデュースアイテム多数。独自の世界観と美意識が絶大な支持を集めている。
TOKYO FM『RADIO DRAGON -NEXT- 』では豊富な音楽知識を生かしてパーソナリティーを担当し、DJとしても活躍。
サウナ好きが高じて熱波師としても活動中。
SNSの総フォロワー数は約100万人に及ぶ。




