トップインタビュー│レコチョクはなぜ、音楽業界で多様な事業を展開できるのか?創業25周年を見据え、不変の価値に迫る


レコチョクは、2001年7月の創業以来、音楽業界のニーズに応じた先進的なサービスを提供・展開してまいりました。
2026年の25周年を迎える今、個人向け音楽配信サービスに加え、法人向け事業も含めたさまざまな新規事業・サービスの芽が育ち、花開こうとしています。これは、創業事業「着うた®」の時代から変わらない使命、そしてこれまで国内音楽業界で培った信頼の蓄積の証です。
では、なぜレコチョクは幅広い事業を展開できるのか……?代表取締役社長 板橋徹にレコチョクの根源的価値、未来への展望に迫るインタビューを実施しました。
(インタビュー実施日:2025年8月)
変化する音楽ビジネスと、不変のミッション

──2010年代末からコロナ禍を挟んでのここ数年間、日本の音楽業界のビジネスモデルは大きく変わりました。その変化についてどう見ていますか?
まず、レコチョクは、音楽市場のビジネスを「音楽そのものを届けるビジネス」と「ファン巻き込み型ビジネス」の2つに分けて考えています。「音楽そのものを届けるビジネス」は、CDなどのパッケージ商品や配信などによって、レコード会社などが権利を持つ音楽原盤を活用するビジネス。「ファン巻き込み型ビジネス」は、ライブ、グッズなど、アーティストとファンとの繋がりから生まれるビジネスです。
「音楽そのものを届けるビジネス」は、レコードの時代から始まり、CDからダウンロード、そしてサブスクへと移行してきました。私の考えでは、これ以上の変遷はないのではないかと思っています。一方で「ファン巻き込み型ビジネス」は現在も大きく変容を続けていて、特に最近は「推し活」を含めたファンビジネスが大きく伸びています。
さらなる市場活性化のためにはこの「ファン巻き込み型ビジネス」をいかに構築するかが重要ではないか、という考えに変わってきており、まだまだ伸びしろがある、というのが2010年代後半から今までの変化と見ています。
──レコチョクは「音楽市場の最大活性化」というミッションを掲げています。いつ頃から、どのような由来でこのミッションを掲げるようになったのでしょうか?
ミッションは創業から変わっていないんです。2001年の創業当時は、楽曲を電子音で再現したMIDI音源を携帯電話の着信音として利用する「着メロ」が人気のコンテンツになっていました。しかし「着メロ」は原盤権利者であるレコード会社には収益が還元されない。
そこで国内主要レコード会社の共同出資として前身である「レーベルモバイル株式会社」※が設立され、2002年にCD音源(原盤)を活用する「着うた」のサービスを始めたという背景があります。その当時の「音楽市場の最大活性化を目的として生まれた会社」という存在意義は今も脈々と受け継がれています。ビジネス領域やサービスは変わってきていますが、使命は変わりません。
※2009年2月に「株式会社レコチョク」へ社名変更
BtoBサービスで広がる新たな可能性

──「着うた」やダウンロード配信が主流だった時代から音楽の聴かれ方は変わってきましたが、レコチョクのビジネスモデルはどのように広がっていったのでしょうか。
2010年くらいまでのフィーチャーフォン時代は、「着うた」や「着うたフル」など、フィーチャーフォン向け音楽配信としてのサービスを立ち上げてきました。そこからスマートフォンが主流になり、レコチョクとしてもアラカルトダウンロードのサービスや、キャリアさんと一緒に「dヒッツ® powered by レコチョク」などの音楽配信サービスを展開してきました。しかしグローバルサービスが競合となるなかで、BtoCの音楽配信一本では競争が難しい。一方で、ミッションとしての「音楽市場の最大活性化」を考えるならば、原盤の活用の仕方はそれだけではない。2016年以降は、法人向けに、サービスやソリューション領域での事業を展開しています。
──BtoBに向けたサービスは具体的にどのようなものがありますか?
まずは「OTORAKU -音・楽-」という店舗用BGM配信サービスがあります。2022年には結婚式場向けに「WEDDING MUSIC BOX」というサービスを開始しました。披露宴のBGMとしてはこれまでCDが主に使われていましたが、権利処理をワンストップで行える配信サービスを提供しています。どちらもUSENさんとの協業によって実現したサービスです。
また、2025年6月には「レコチョク play」という法人向け原盤歌唱の許諾スキームを開始しました。従来のカラオケはMIDI音源が主流ですが、新たに原盤音源での歌唱が可能になりました。原盤音源での歌唱に加え、カラオケメーカーさんの機器開発によって、ボーカル音量のコントロールができるなど、新しい楽しみ方ができるようになったのも大きな特徴です。得意な部分だけを歌ったり、アーティストとデュエットのように一緒に歌ったりすることもできる。こうした新しい音楽体験を作る仕組みを支えるのは、まさに我々がやるべきところだと考えて、事業領域を増やしています。
──特に原盤を用いたカラオケのニーズは大きいと思います。今までなかったのが不思議なくらいです。
カラオケに原盤利用スキームを提供するというのは7年くらいかかった構想でした。これは非常にレコチョクらしい着眼点だと思います。というのも、「着うた」と同じく、MIDI音源ではレコード会社のような原盤権利者には収益が発生しないというところから生まれた発想なんですね。原盤を活用することによって、権利者に収益を還元できる。ユーザーの体験価値も上がる。レコチョクの根源的な価値を発揮することで、三方よしの座組を実現できたのではないかと思います。現時点ではコシダカさんの運営する「カラオケまねきねこ」のエンタメプラットフォーム「E-bo」が導入されている店舗で展開していますが、これからカラオケメーカーさん各社と協力して広げていきたいと思っています。
国内音楽業界への知見と信頼が強み

──そういったサービスを立ち上げるにあたってレコチョクの優位性は?
音楽の新しいサービスモデルを立ち上げていくにあたっては、複雑な権利処理が課題になります。しかしレコチョクはもともと「音楽市場の最大活性化」をミッションに生まれた会社であり、国内音楽市場への理解があり、音楽業界内、特にレコード会社との信頼関係もできている。ここにレコチョクが存在する意義がある。ポジショニング上の優位性というのも当然あると思いますが、我々のミッションと合致しているところが大きいですね。
──ソリューション事業についてはどのようなサービスがありますか?
先ほど申し上げた「音楽そのものを届けるビジネス」と「ファン巻き込み型ビジネス」、それぞれのビジネス領域において現状の課題を解決できるものや、新しい機会の創出ができるものは何かを考え、いくつかのソリューションを提供してきました。ひとつは「murket(ミューケット)」という音楽業界・コンテンツホルダー向けのワンストップECソリューションです。こちらは権利者による直販ストアの立ち上げを我々がサポートしています。
また、「P!TNE(ピトネ)」というサービスを開発して提供しています。これは、会員登録不要のアプリをダウンロードすれば、NFC技術を活用してアクリルスタンドなどのグッズにスマホをかざすだけで音楽が流れるというアプリです。アーティストからのボイスメッセージを聞いたり限定の映像を見たりすることもできる。フィジカルなグッズにデジタルを組み合わせることで、新しい商材開発につながる。こうした取り組みは「ファン巻き込み型ビジネス」領域のソリューションです。
一方で「音楽そのものを届けるビジネス」の領域においては、2025年7月に子会社である株式会社エッグスとの協業で立ち上げた「FLAGGLE(フラグル)」という法人向け音楽配信支援ソリューションがあります。こちらはグローバル標準の配信環境を整備し、預かった楽曲を全世界にディストリビューションするだけでなく、音楽配信業務のコンサルティングサービスや、配信用の楽曲データベースの整備などの細やかな業務サポートを提供します。
──ソリューション事業はレコード会社などの権利者を対象にしたものですよね。そこにビジネスとしての課題や、未開拓の機会があるという認識から事業が始まっている。
権利者の課題解決と、新しいビジネスチャンスの創出につながるものを提供しようという考えがあります。「FLAGGLE」に関しても、ディストリビューションの運用まで我々の方でサポートしようという発想の背景には、やはり課題解決があります。
レコード会社の皆様からお話を伺う中で、音楽業界の発展には、本質的に良い音楽を生み出し続けることが不可欠であり、そのために創造的活動に引き続き重点を置きたいといったお考えを共有いただいています。ただし、その生み出した音楽を確実に届けるためのDX化やオペレーション面のサポートも専門領域として必要性が増しており、全体的なバランスを図ることが業界としての大きな課題として捉えています。
であれば、オペレーションやマネタイズの仕組みについては我々がソリューションを提供する。課題になっているDX化の部分を我々の技術力でサポートするのがベストだろうと思います。レコチョクは音楽業界から生まれた会社であるというバックボーンもあり、「音楽市場の最大活性化」というミッションを果たすために必要なことのひとつだと思います。
──アーティスト支援事業についても聞かせてください。特に「Eggs」はインディーズアーティストの登竜門のようなサービスになっていると思うのですが、こちらに関してはどういう狙いがありますか。
これもやはり「音楽市場の最大活性化」というミッションに基づいています。「Eggs」のようなプラットフォームを作ることによって、音楽をやっている若い世代のアーティストが世の中に出ていくための支援ができる。我々のサポートが音楽市場の最大活性化につながるのではないかというところからスタートしています。「Eggs」を使っていただいているアーティストの数も大きく増えていますし、そこからメジャーデビューして活躍している方もたくさんいらっしゃる。そういった意味でも、これまでやってきた成果はあったのではないかと思っています。
「音楽市場の最大活性化」を加速させるプロフェッショナル集団へ

──板橋さんは、以前のインタビューで、「レコチョクは音楽業界のIT部門」ともおっしゃっていました。エンジニア集団としての技術力が会社の強みになっているという側面もあるのではないでしょうか。
実は社員の40%以上がエンジニアなんです。以前は業務委託や外部のベンダーに発注していましたが、この10年間は開発を内製に切り替え、新卒のエンジニアも採用し、アウトプットレベルを上げていく取り組みを続けてきました。結果として音楽ビジネスへの知見をもつ自社のエンジニアが、熱量をもって開発している。そこは我々の大きな強みだと思います。たとえば2025年5月に第1回が開催された国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」では音楽業界関係者5,000人以上が参加した投票システムを自社で開発しました。音楽業界に対して技術力を還元できたシンボル的な事例だと思います。
──この先のビジョンについてもお伺いします。レコチョクをどういった会社にしていきたいという考えがありますか?
我々の強みや誇れる実績として、音楽の領域では日本で一番サービスモデルを立ち上げてきた会社というのがあります。「着うた」から始まって、リングバックトーンも、ダウンロードも、ストリーミングサービスもやっています。そして、新しいサービスモデルも展開している。レコード会社とこれまで交わした契約書の数は日本で一番多いのではないかと思います(笑)。
これからもどんどん新しいサービスモデルを立ち上げていかなければいけないと思っています。社員はみな権利者やユーザーのためになる新しいサービスモデルを立ち上げるプロフェッショナルになってほしい。レコチョクという会社がそのプロフェッショナル集団になっていくことが僕の理想です。
──音楽ビジネスの中でのレコチョクという会社の長期的な展望に関しては、どのように考えていらっしゃいますか?
レコチョクが提供する普遍的な価値は、社会のあらゆる場面で音楽を単に聴くためだけでなく、もっと自由に活用できる環境を整えることにあります。これには、音楽を利用したい人々がその機会を手軽に増やせるようサポートしたり、権利者のシステムを支える体制を提供したりすることが含まれます。また、利用者と権利者を結ぶための許諾や申請、複雑な権利処理を円滑に進めることも重要です。
私たちは、「音楽そのものを届けるビジネス」「ファン巻き込み型ビジネス」の両分野において、新しいサービスモデルを提供し、利用者が音楽をさらに手軽に利用できる仕組みを作り出します。これが今直近で見えている、我々がやるべき「音楽市場の最大の活性化」への道だと確信していますし、実績として自負できるところです。
これまでの社員の努力の成果もあって、業界内での信頼が私たちの大きな強みとなっています。これからも、音楽市場のさらなる活性化を目指して進んでいきたいと思っています。
取材・構成=柴那典(音楽ジャーナリスト)
撮影=平野哲郎
-
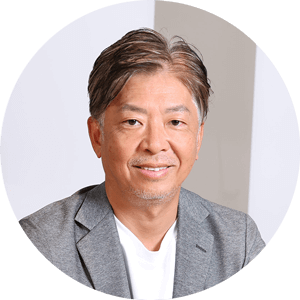
板橋徹(いたばしとおる)
1974年生まれ。
バンダイに入社しネットワーク事業でプロモーションやマーケティングを担当後、ベンチャー系モバイルサービス会社へ。
2008年にレコチョク入社。配信事業部長、執行役員、取締役を経て、2021年に代表取締役に就任。


